- 転職したいけど、何から始めれば良いのかわからない
- 転職活動していること、会社にバレない?
- 履歴書や面接でアピールできることがない
初めての転職、不安ですよね。
転職活動の不安は具体的な「スケジュール」と「手順」を理解すれば解消することができます。
転職に必要な期間はおよそ3〜6ヶ月。
この間に自己分析や業界・企業研究、応募、面接、給与などの条件交渉、現職の引き継ぎ、退職手続き、入社手続きと数多くのことをこなす必要があります。
筆者は建設業界で15年以上のキャリアを重ね、さまざまな企業の担当者と関わってきた経験から、業界の実情について精通しています。また自身も複数の転職エージェントに登録し、実際に転職活動を継続しているため、転職者目線でのリアルな情報を提供することができます。
そこでこの記事では、建設業界で転職活動をする人向けに、転職活動の基本からスケジュールの立て方、職務経歴書や履歴書の書き方、面接対策、退職手続きまで、転職の全体像を幅広く解説します。
この記事を読めば、
- なんとなく不安だからと二の足を踏んでいた人
- 今まさに転職活動中だが、迷走中の人
そんな人も成功率の高い転職活動の第一歩を踏み出すことができます。
私自身の体験や転職に関する記事・書籍の内容を凝縮しています。建設業界での転職を成功させたい人は、ぜひ最後まで読んでください。
ステップ0:転職活動の基礎知識
転職活動の流れ
転職活動は大きく5つのステップに分けられます。

面接対策に意識が向きがちですが、本当に差がつくのは準備段階です。自己分析や業界・企業研究をどれだけ深められるかが、成否を決めるカギになります。
転職活動はノーリスク
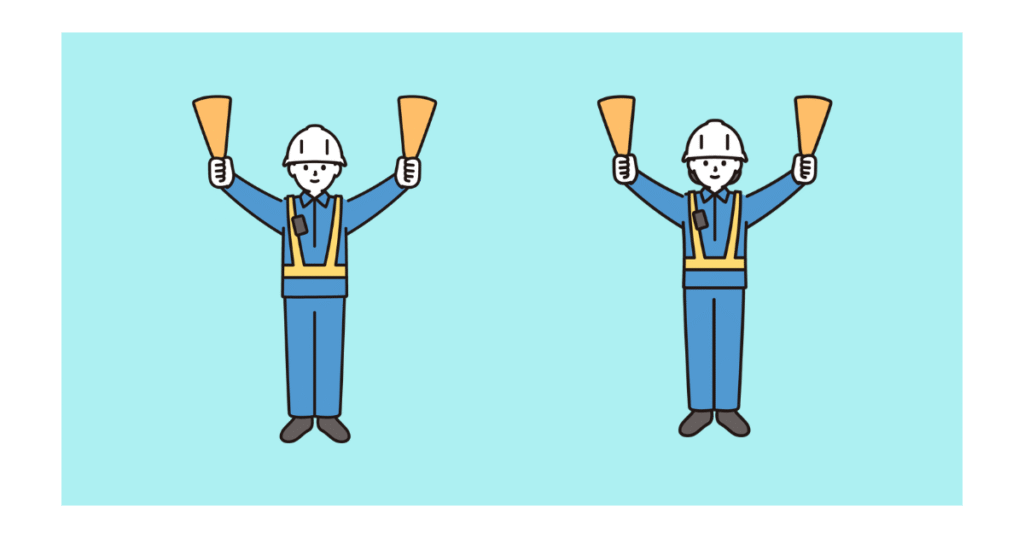
「転職活動」と「実際に転職すること」は異なります。
自己分析や情報収集を行っても、現在の仕事に支障が出ることはありません。むしろ、求人票などから必要とされる経験やスキルを知ることで、今の働き方を客観的に見直す機会となります。
転職活動はキャリアの可能性を広げるための手段であり、取り組むことで得られるメリットは大きく、活動だけであればノーリスクです。費用も交通費やスーツ代を考えても10万円未満と負担も少なく、やらない理由がありません。
在職中の転職活動と退職後の転職活動の違い
転職活動を在職中に行うか、退職後に行うかで取り組み方が変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットは次の通り。
✅️在職中に転職活動するメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 生活費の心配がない 離職期間がない | 準備に時間がとれない 面接の日程が決まりにくい |
✅️退職後に転職活動するメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 準備に時間がとれる 面接の日程調整がしやすい | 生活費の心配 離職期間ができてしまう |
在職中の転職活動は、現職の業務と並行して行わなければならないため、時間のやりくりが大きな課題です。そこで頼りになるのが転職エージェント。希望に合った求人紹介だけでなく、職務経歴書の添削、企業との日程調整や年収交渉までサポートしてくれるため、効率的に活動を進められます。
一方、退職後の転職活動は時間を確保しやすい反面、収入が途絶えるため精神的な負担が大きく、生活資金の備えが欠かせません。また離職期間ができると面接で理由を問われることもあり、納得感のある説明が求められます。
時間に余裕がある点は魅力ですが、収入がないプレッシャーから妥協した転職に至るリスクもあります。そのため、安定収入を確保しながら活動できる在職中の転職活動をおすすめします。
求人情報をどこから手に入れるか?
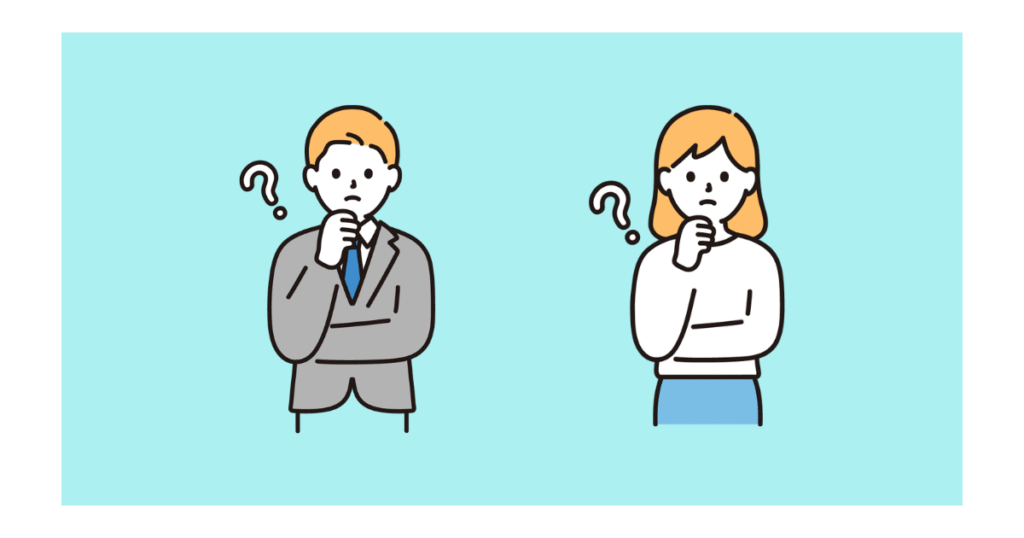
転職活動では、求人情報をどこから得るかがポイントになります。転職サイトが代表的ですが、大きく次の5つに分類されます。
いわゆる「コネ」です。最近では「リファラル採用」とも呼ばれます。その企業の関係者が「この人は」と思った人を連れてくるといった採用形式です。
自社のサイトで直接求人をかける方式です。知名度の高い企業の場合には応募が殺到し、大量の応募書類を採用担当者が確認する必要があるため、あまり吟味されずに書類選考の段階ではじかれるリスクもあります。
リクナビNEXTやdoda、マイナビ転職などが有名です。転職サイトのメリットは同じフォーマットで企業の比較ができるため、年収相場やその業界で求められているスキルを把握しやすい点にあります。
一方で、コーポレートサイトと同様に1つの求人に対して応募が殺到する場合には書類選考ではじかれやすいというデメリットもあります。
転職エージェントは、企業と転職希望者の間に立ってサポートを行う存在です。最大の魅力は、応募書類の添削や模擬面接、企業との日程調整など、転職活動をトータルで支援してくれる点にあります。
ただし、エージェントは成果報酬型の仕組みで運営されているため、企業に紹介しやすい=内定の可能性が高い人材を優先しがちです。そのため場合によっては十分なサポートが得られないケースもある点は注意が必要です。
国が運営する職業紹介所です。無料で求人を掲載できる上、採用が決まれば国から補助金が出るため企業にとってはメリットがあります。そのため採用にコストをかけたくないという企業が集まりやすく、特に都市部では魅力的な求人が少ないという傾向があります。
転職エージェントと転職サイトの違い
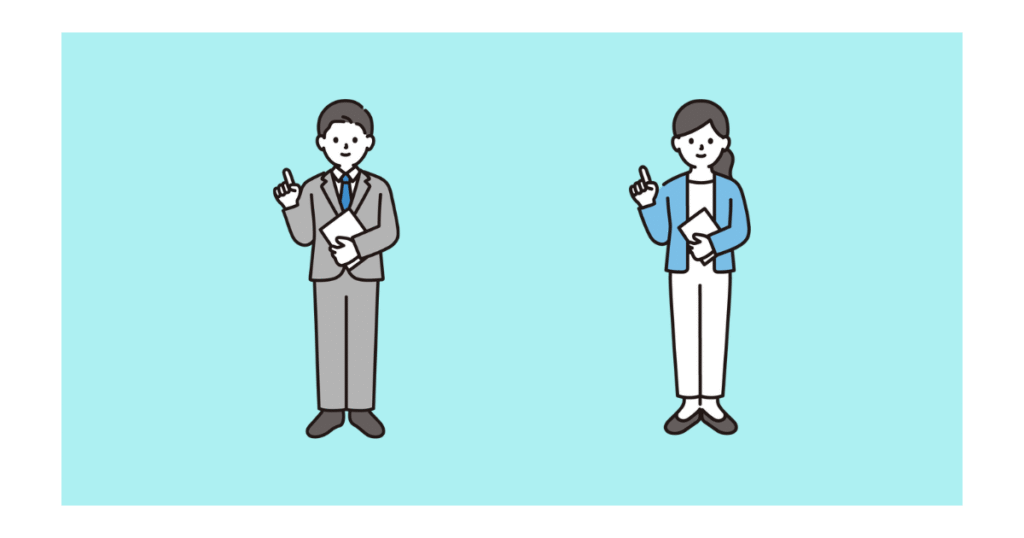
転職エージェントと転職サイト、今ひとつ違いがわかりにくいですよね。両者の違いを理解した上で転職活動を進めましょう。
【転職エージェント】
- 求人紹介から履歴書添削、面接指導まで転職全体に渡るサポートがある
- そのエージェントしか持っていない非公開求人が多数存在する
- 求人企業は人材採用にお金をかけられる財務体質であることが保証されている
企業は採用者の年収の約3割という高い成果報酬をエージェントに支払います。そのため、財務体質がしっかりとしており、求人のお金をかけることができる優良求人が多く集まっていることが特徴です。
【転職サイト】
- 自ら応募して選考を進めるため、自分のペースで活動したい人に向いている
- 転職エージェントのようなサポートはない
- 大量採用の求人が集まりやすい。大量採用の背景に常に大量の離職者がいる可能性もあるため要注意
初めて転職活動を行う場合や、在職中に行う場合には手厚いサポートが受けられる転職エージェントを主体に活用し、並行して転職サイトで年収相場や業界動向といった情報を集めておく、といったやり方がおすすめです。
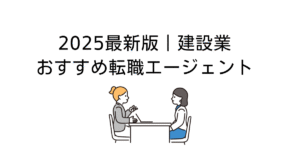
軸ずらし転職とは
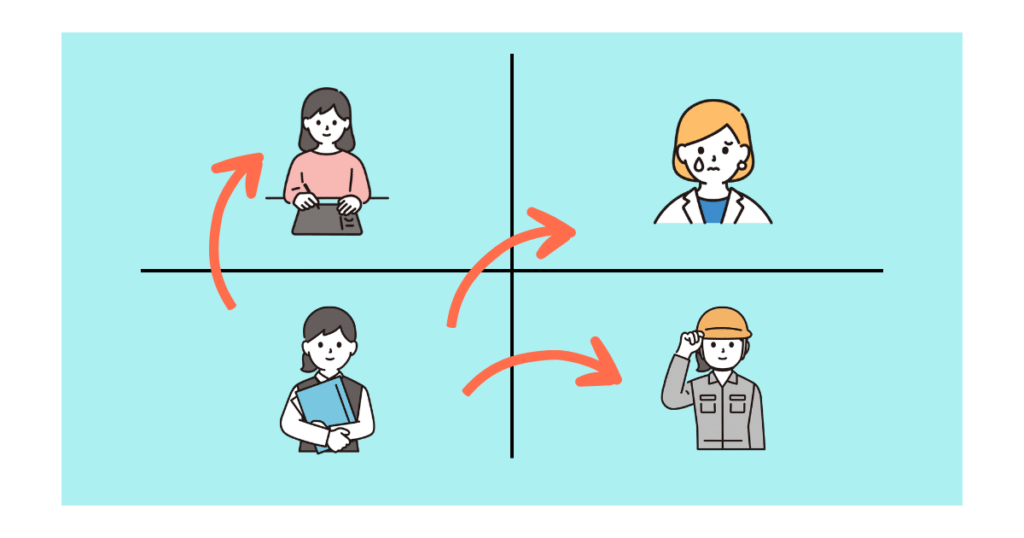
年収は主に「業界×職種」の組み合わせで決まります。この「業界」と「職種」のどちらか一方だけを変える転職を軸ずらし転職と呼ばれています。
例)小売業の営業 → 建設業の営業
なぜどちらか一方だけを変えるのかというと、両方変えてしまうと今までの自分の経験が活かせず、失敗する可能性が高くなるからです。
年収は役職や企業規模も関係しますが、大きな要素は「業界×職種」です、業界が異なれば役職と年収が逆転することもあります。
例えば、
業界は年収に大きく影響します。お金が大きく動いて、儲かる業界に移ることが年収アップのカギです。
その意味では建設業は年収アップに最適な業界と言えます。
ステップ1:事前準備/応募(2〜4週間)

転職成否の9割は「準備」の質で決まると言われています。面接での受け答えなどに目がいきがちですが、この準備の段階で「転職の軸」をしっかりと定めておかなければ、面接本番でボロが出てしまいます。
では具体的にどのように準備をすすめて行けばよいのか、見ていきましょう。
転職活動開始を宣言する
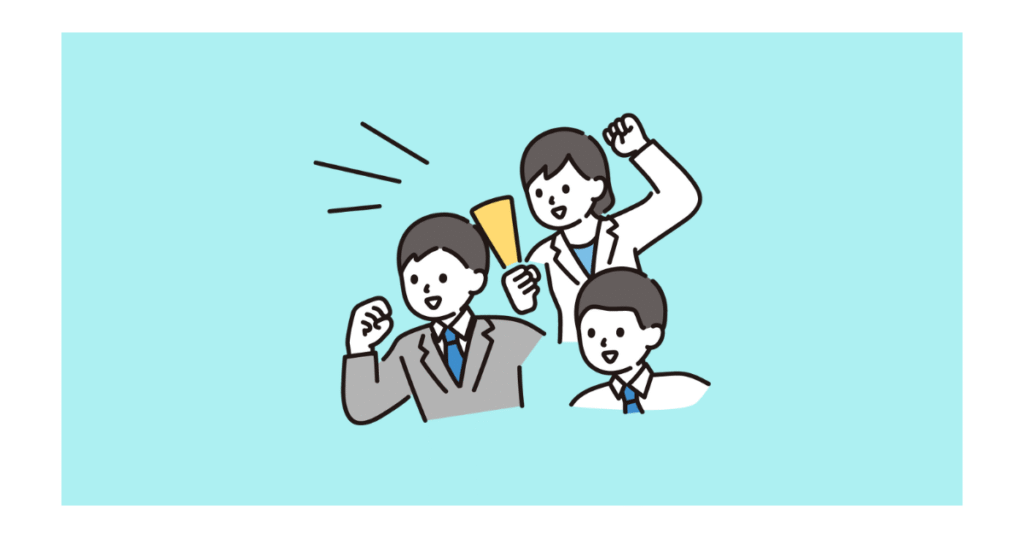
転職活動を始める際には、まず「社外の人」に活動を始めることを宣言することをオススメしています。宣言することでプレッシャーが原動力になります。特に家族には内定後に反対されないよう、あらかじめ宣言しておくと良いでしょう。
当然ですが、どんなに仲の良い同僚であっても「社内の人」に打ち明けることはNGです。「社内」に対しては、内定獲得後、退職の報告をする際に直属の上司に対して伝えるのが最初です。
またこの段階から早めに引継書を作成しておくと、応募書類の参考になるだけでなく、面接時の受け答えにも役立ち、実際の業務引き継ぎもスムーズに進めることができます。「まだ早い」と思わず、できることから少しずつ整理していきましょう。
転職の軸を決める
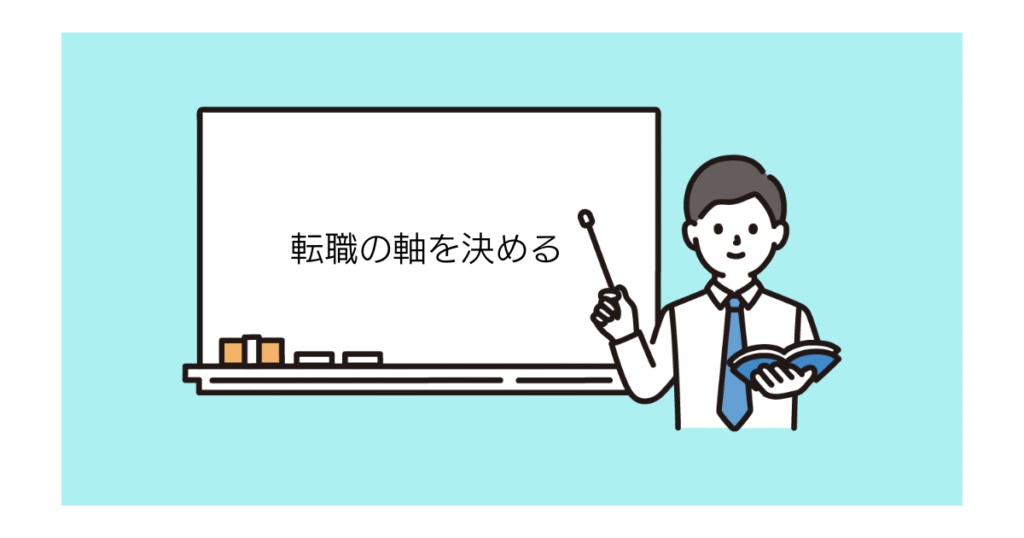
- 定時上がり
- 年収アップ
- スキルアップ・・・
一度に全ての希望を叶える転職をすることは困難です。
これだけは譲れないというラインを明らかにするために、希望を数値化してランキングにすることをおすすめします。数値化、言語化しておくことで、他人の意見に流されにくくなります。
具体的な目標とスケジュールをたてる

目標とデッドラインを決めることで、行動を起こす原動力となります。目標倒れにならないよう、具体的な数字を入れましょう。
例)目標:3ヶ月以内に転職して1年以内に年収150万アップ
目標を立てたら、それを達成するためのスケジュールを立てます。
分析1週間、調査2週間、応募2週間、練習2週間、面接4週間、退職2週間のように、スケジュールにも数字は必ず入れます。このときのポイントは100点を目指さないことです。
まずはざっくりとした予定を立て、行動しながら修正していけばOKです。
「将来ありたい姿」を具体的に想像する
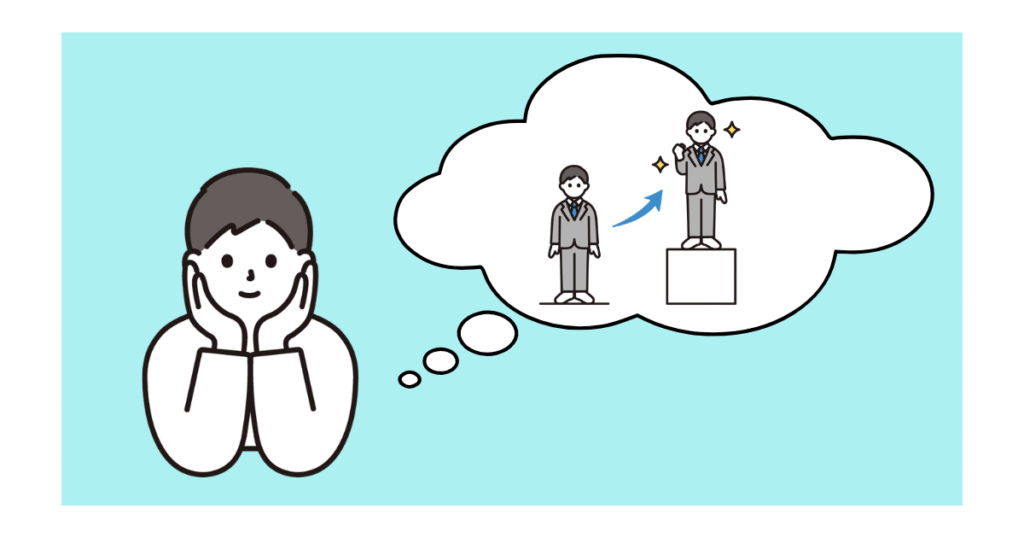
今後(例えば10年後)の自分がこうなっていたいという姿を具体的に、またそうなりたい理由も含めて考えます。
- どんな仕事内容で、どれくらい働いているか
- どんな仲間と仕事をしているか
など、楽しくイメージすることがポイント。
その姿が、転職活動という手段を用いて目指したいゴールとなります。
紙やパソコンに書き出していき、解像度を高めましょう。
現在の自分の「タグ」を明らかにする
目指すゴールが解像度高く想像できたら、次はキャリアの棚卸しをします。自分がもっている「タグ」を明確にしましょう。「タグ」とは自分の手持ちスキルや得意分野、経験のことを指します。
自分のタグを明らかにすることで、タグを活かせる仕事=充実できる楽しい仕事を見つけやすくなります。また、タグは企業に対して提供できる価値ですので、応募書類や面接においてはアピールポイントとなります。
将来ありたい姿と現状のギャップを把握する
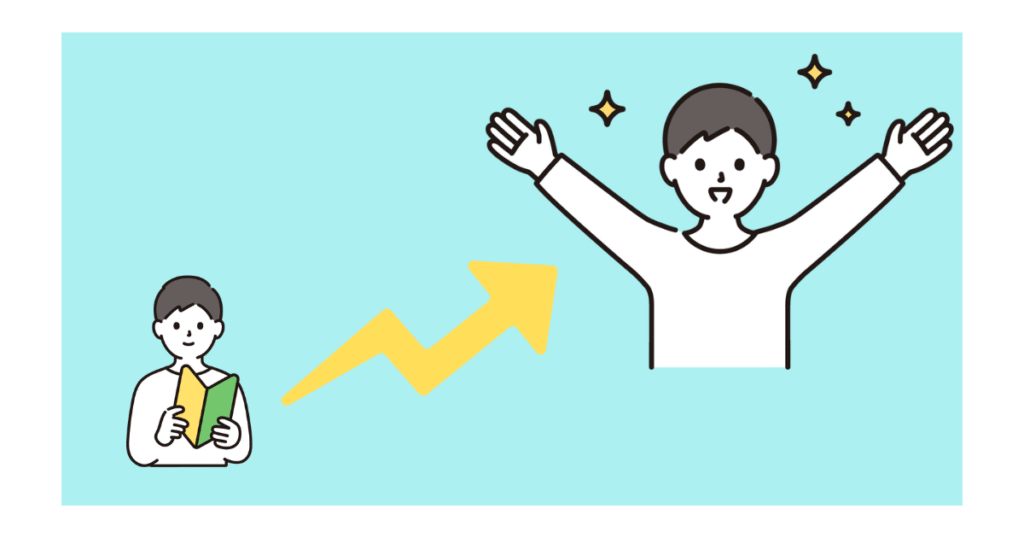
ここまでで、自分が理想とする姿と現状とのギャップが把握できました。次はこのギャップ(=足りないタグ)を埋めるために、具体的にどのようなアクションを取って行けば良いのかを考えます。
ギャップを埋めるためには、経験を積む必要があります。
ただ、多くの場合、理想と現実とのギャップは大きく、一度の転職でこのギャップが埋まることは稀です。
そこで重要なのが、転職を何度か重ねる中で、必要なタグ(=知識や経験)を手に入れ、自分の理想像に近づいていくという考え方です。
すごろくやゲーム感覚でこの足りないタグを集めていく考え方が、転職を成功させる上で重要になってきます。
転職エージェントに登録する
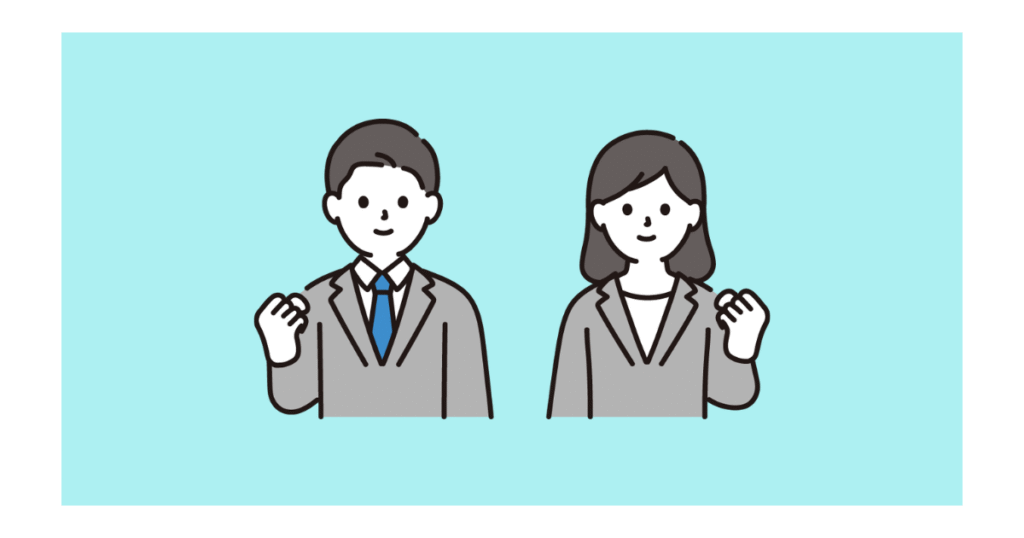
自分に足りないタグが明らかになった段階で、転職エージェントに登録し、求人の紹介を受けます。
今までどのような経験を積んで、どのようなスキルがあり、将来どのような経験を積みたいのかが明らかになっていますので、自分の希望にマッチした求人紹介を受けることができます。
また、この時紹介される求人やスカウトの内容から、自分の市場価値を客観的に知ることができます。
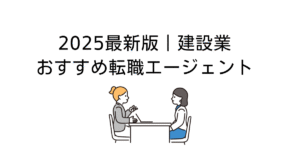
業界・企業研究をする
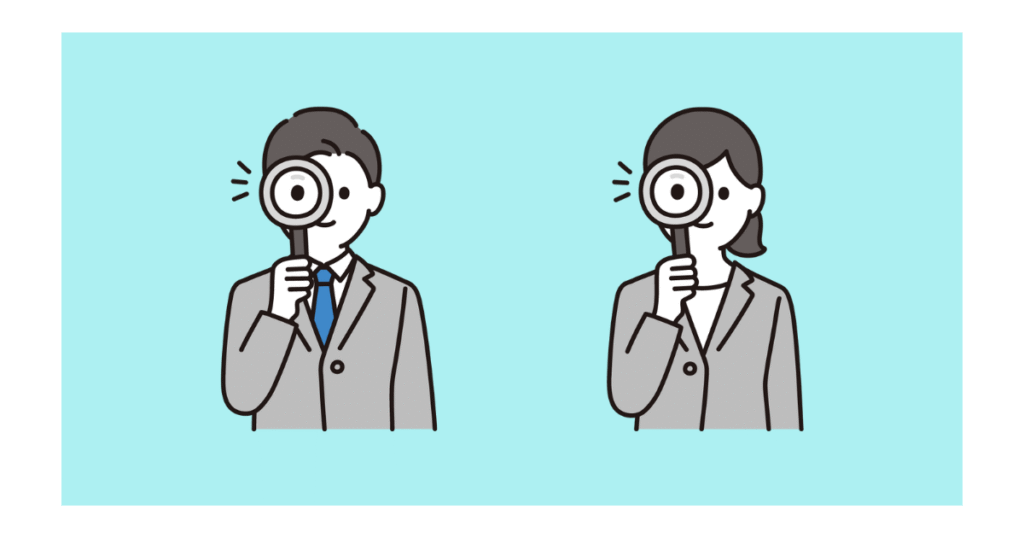
業界研究・企業研究を行うのは新卒就職活動と同じですが、同業界への転職でも必ず行うようにしましょう。長年その業界にいることで、逆に見えなくなっている観点があるかもしれません。
企業研究では社員紹介やインタビューを確認するのがおすすめです。ただし、企業公式サイトの内容は、良い内容だけを書いていますので、転職口コミサイトも確認しバランスを取るようにしましょう。
企業研究を行う際には、自分に足りないタグ(=知識や経験)を得ることができそうか、という観点で行います。必要なタグを得られそうな企業であれば、強い志望動機となります。

〇〇の経験を積んでスキルアップしたいと考えており、御社であればそういった経験を積むことができると考え、応募いたしました
といった感じで志望動機を語ることができます。
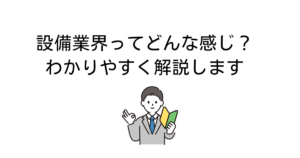
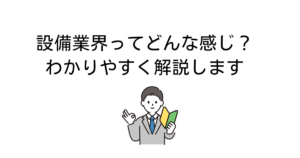
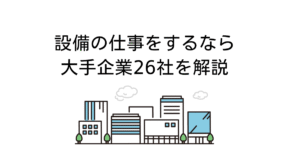
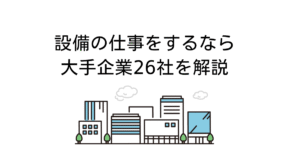
応募書類を作成する
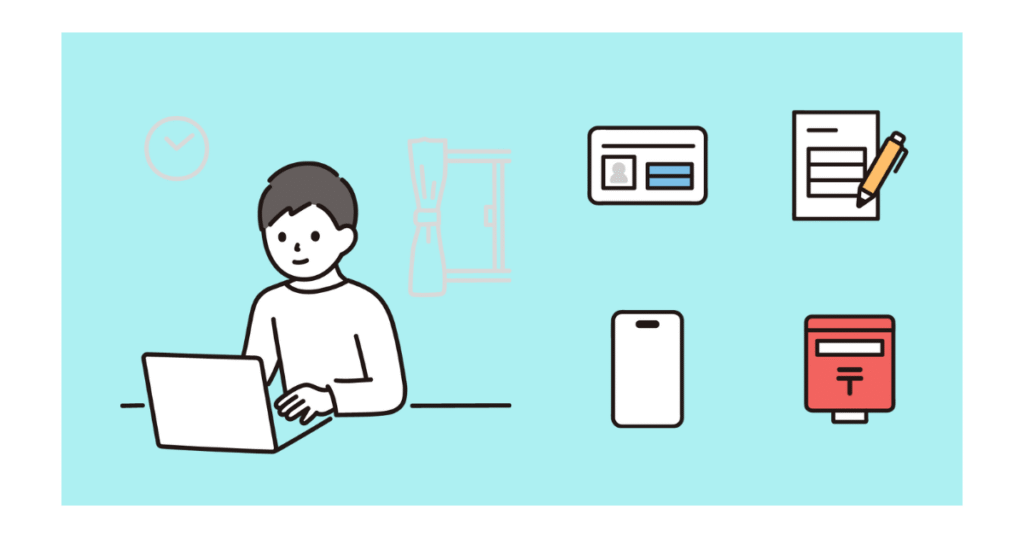
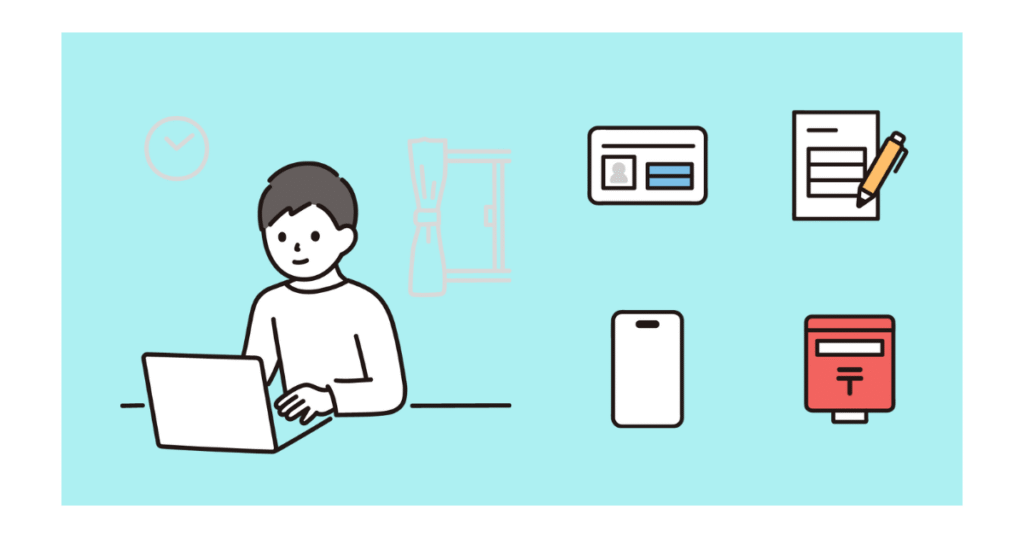
応募書類には履歴書と職務経歴書があります。
履歴書は採用担当者が最初に目にする書類であり、第一印象を左右する重要なものです。写真は3ヶ月以内に撮影し、ビジネスにふさわしい服装で正面を向いたものを使用しましょう。
職務経歴書には趣味や特技など、仕事に直結しない情報は不要です。面接での質問は基本的に職務経歴書をベースに行われるため、記載した内容は具体的に説明できるよう準備しておく必要があります。
職務経歴書を作成する際には、自分の市場価値を意識して作成することが大切です。応募企業の視点に立ち、募集ポストに合った強みやスキルを書くことで、自分がどういった価値を提供できるのかが明確になるため、書類選考の通過率が大きく高まります。
さらに、仕事に取り組むうえでの工夫や意識を具体的に言語化したり、自分の短所についても自覚と改善への姿勢を示すことで、書類の説得力が増します。
応募書類が完成したら、必ず担当エージェントの添削を受け、第三者の視点から改善点を洗い出し、より完成度の高い書類に仕上げましょう。


求人に応募する
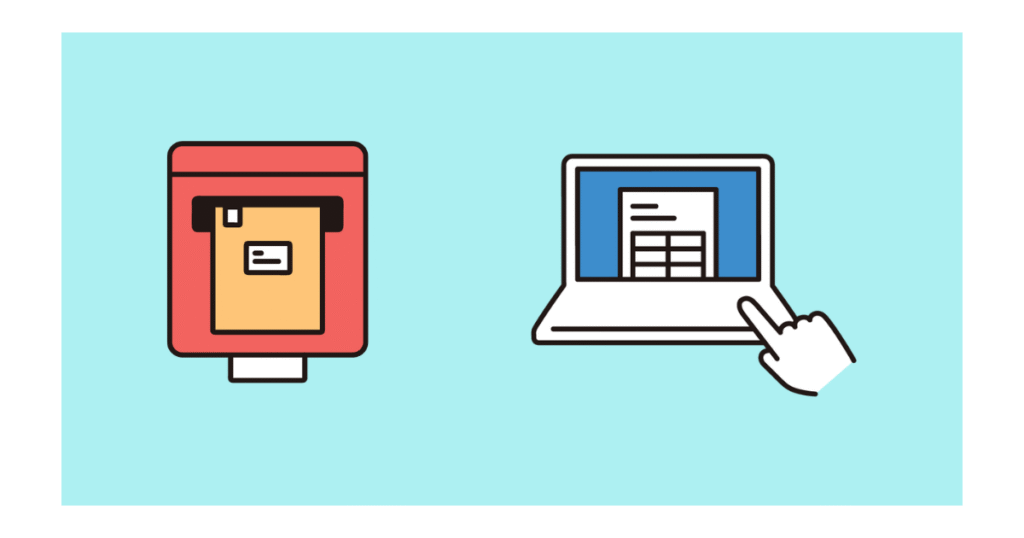
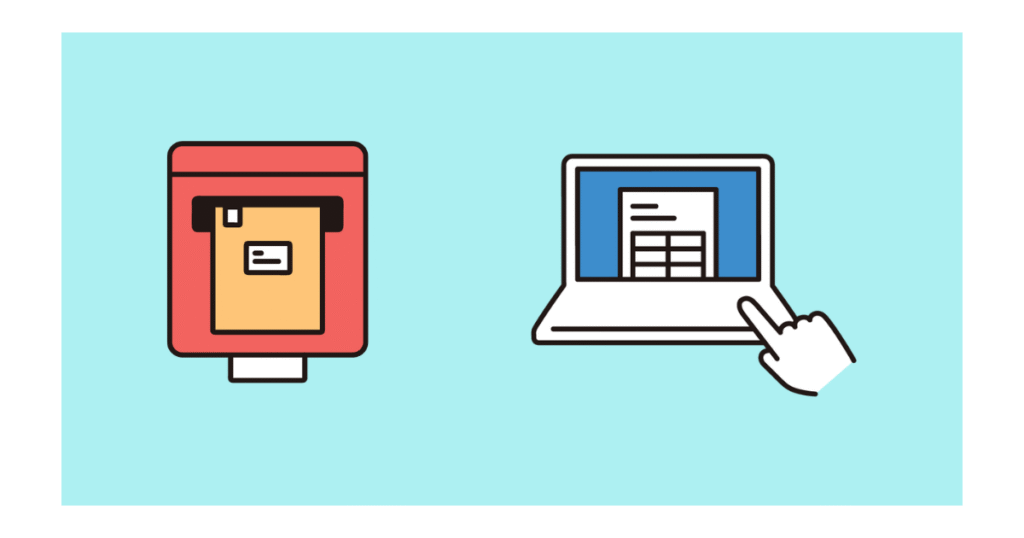
準備が整ったら求人へ応募します。担当エージェントへ応募の意思を伝えれば、企業との日程調整などはエージェントが行ってくれます。応募は1社だけでなく、複数同時に応募することで企業特性の理解が早まります。
条件にこだわりすぎて理想の求人が見つからず、転職活動が長期化するといった失敗例もありますので、譲れないことと妥協できることを明確にしておくことが大切です。
応募にあたってはスピードが重要です。迷っている間に魅力的な求人がクローズしてしまうことも珍しくありません。多くの転職希望者が20社以上に応募している現実も踏まえれば、早めに事前準備を進めておくことが有利に働きます。
ステップ2:面接(1〜2ヶ月)


中途採用面接は通常1〜3回行われます。本番までに何度もエージェントと模擬面接を行いましょう。どんな質問がきて、何を見られていて、何を答えれば良いのか、担当エージェントとすり合わせを行います。
オンライン面接も増えているので、聞き取りやすい話し方や、表情の作り方を意識して練習に取り組む必要があります。スマホで録画しながら、声のトーン、話すスピード、表情をしっかりチェックしましょう。普段より滑舌よく話し、相槌も大きめにうつ意識を持って面接に臨みます。
面接では①自己紹介・自己PR、②転職理由、③志望動機、④活かせる経験・実績・スキル、⑤逆質問(面接官への質問)、の5つはほぼ間違いなく聞かれます。
- 前職での具体的な業務内容を教えてください
- 前職で達成した成果や学んだことは何ですか?
- 仕事をする上で大切にしていることは何ですか?
- 5年後、10年後にどのようなキャリアを築きたいですか?
- あなたにとって仕事とは?
- 当社で挑戦したいことはなんですか?
こういった質問に対する答えを事前にしっかりと準備しておきましょう。
また可能であれば、1次面接の段階で年収交渉を行うことが望ましいです。付き合いの入口の段階で価値観をすり合わせておくことで、お互い時間を無駄せずに済むからです。担当エージェントとも相談し、交渉のタイミングを測りましょう。
ステップ3:内定(1〜2週間)


面接を無事通過すれば、晴れて内定獲得です。内定を受けるかどうかの回答締切は1週間程度が相場です。
通常は内定承諾前にオファー面談(雇用条件をすり合わせる目的で実施される面談)が行われます。
面接後にその場で入社手続きを勧められることもありますが、その場では応じないようにします。優先順位を常に意識しておき、時間をおいて冷静に考えた上で回答しましょう。
内定後、企業から交付される労働条件通知書の内容は必ず確認します。法律で交付が義務付けられているので、交付がない場合は問い合わせるか、辞退した方が良いでしょう。内容が認識と異なっている場合には、我慢したりせず採用窓口・オファー面接で相談・確認するようにしましょう。
ステップ4:退職/引き継ぎ(1〜2ヶ月)


転職活動は内定を獲得すればゴールではありません。内定承諾後、引き継ぎ・退職のフェーズに移ります。
まずは退職報告を直属の上司に行います。民法上、退職を申し入れた2週間後に雇用契約を解消できると定められていますが、円満退社のため、退職までの期間は最低1ヶ月確保した上で報告を行います。企業の就業規則に定められている場合もありますので、事前に確認が必要です。
この時重要となるのが、退職の「相談」ではなく、退職するという「決定事項」を伝えるという意識で望むことです。
相談ベースで話を持ちかけると、引き止めに合う可能性がより高くなり、下手をすれば丸め込まれて内定を辞退するということにもなりかねません。
引き止めに勝つにはただ強く耐えるしかありません。この時、何があっても不満や悪口を言わないこと。返答に困ったら笑顔で感謝を伝えて乗り切りましょう。
現職企業が転職を妨害するトラブルも発生しているため、転職先を同僚や上司に伝えることも避けたほうが無難です。
退職の報告が完了したら、漏れがないように担当業務をリスト化し、引き継ぎを行っていきます。準備段階で引継書を作成していれば、スムーズに進むはずです。
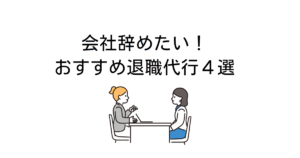
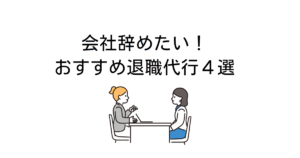
ステップ5:入社後


転職活動のゴールは転職後の企業で活躍することです。入社後はすでにいるメンバーから「どんな人なのか?」と様子を見られる期間が必ずあります。
入社直後は焦って自分を売り込むのではなく、周りのことを理解する姿勢が大切です。前職での実績を口にしたり、やり方を押し通すようなことは避けましょう。
仕事でわからないことは周りの人に素直に聞くなど、関係をつくることに注力します。特に社内のキーパーソンを見つけることが、人間関係を構築する上では非常に重要です。
入社直後は人間関係の構築に注力し、その後ビジネスの状況を理解して自分のやるべきことを見つけます。
そして入社3ヶ月を目処に、自分のやるべきことの中から徐々に成果を出していくように行動していきましょう。
まとめ
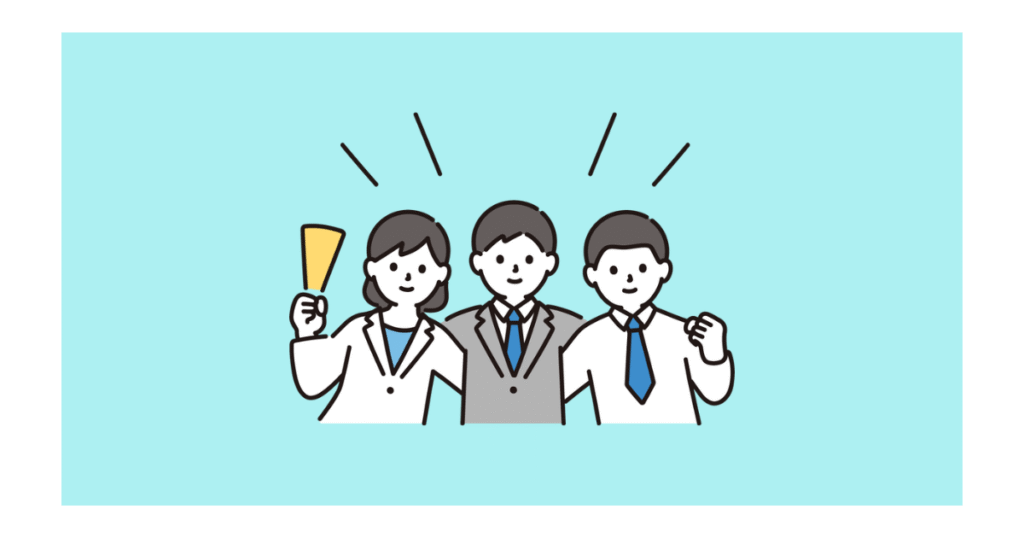
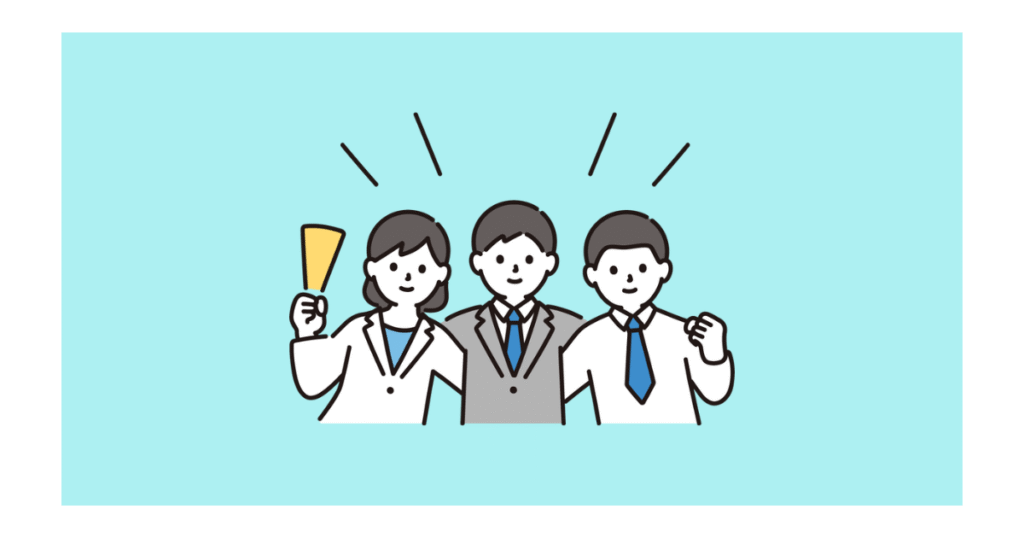
ここまで、転職の基礎知識から準備、そして入社後に取り組むべきことまでを5つのステップに分けて解説してきました。
実際に転職することにはリスクが伴いますが、転職活動そのものはノーリスクです。むしろ、自分のキャリアを見直し、今後のスキルアップや年収アップにつなげるための有効な手段と言えるでしょう。
転職の成否を左右するのは、何よりも“準備の質”です。10年後の理想の姿を思い描き、そのために不足しているものは何か、どの企業ならそれを得られるのか、そして自分はどんな価値を提供できるのかを具体的に考えることが重要です。
転職の軸を明確にし、入念に準備を重ねていけば、必ず次の道は開けます。この記事がその一助となり、皆さまの転職活動が実りあるものになることを願っています。
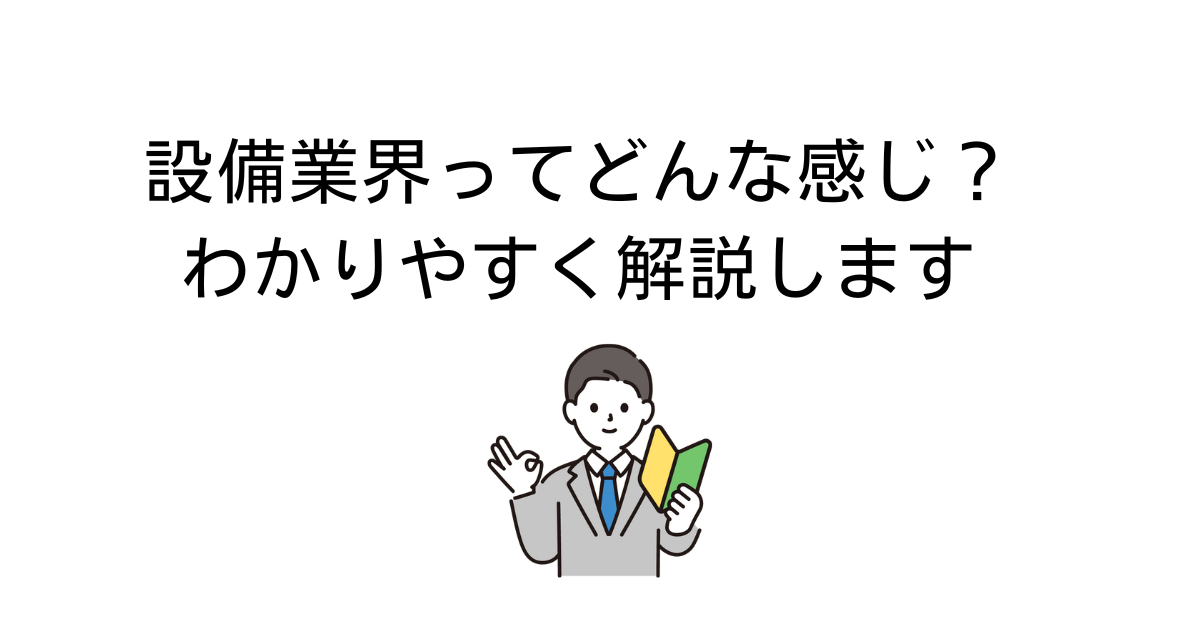
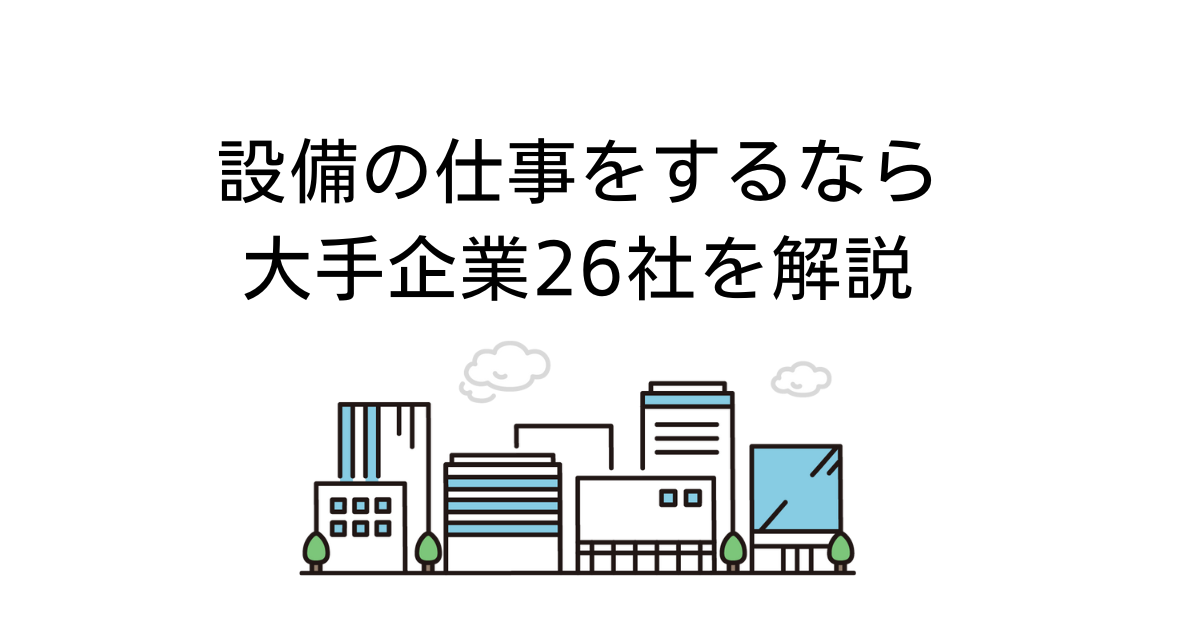
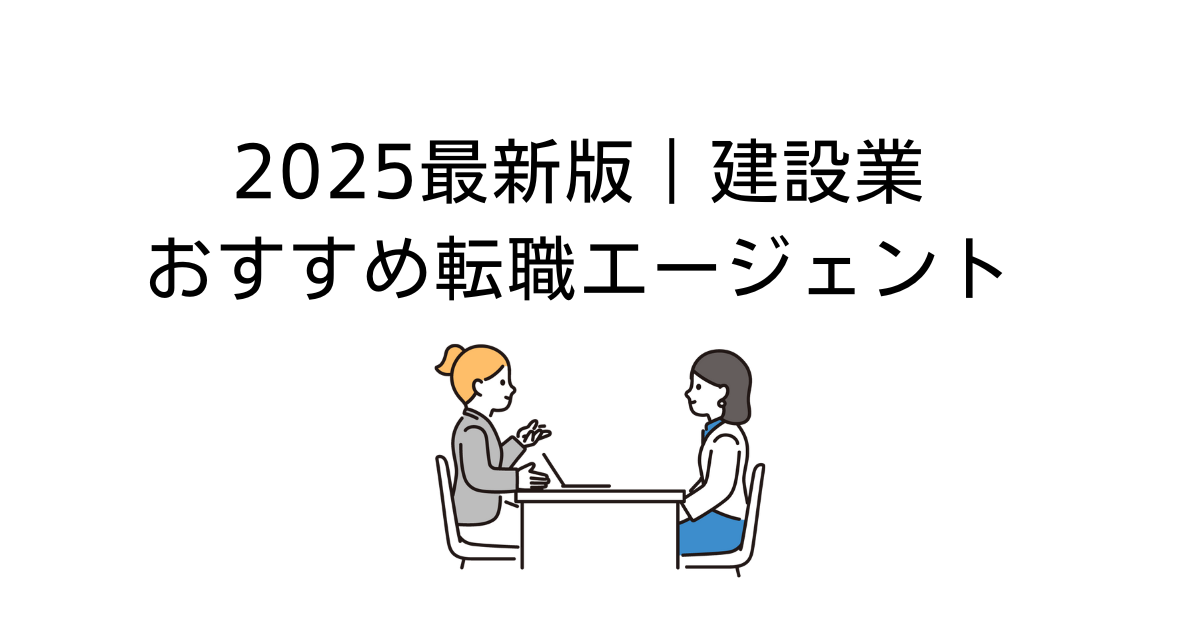
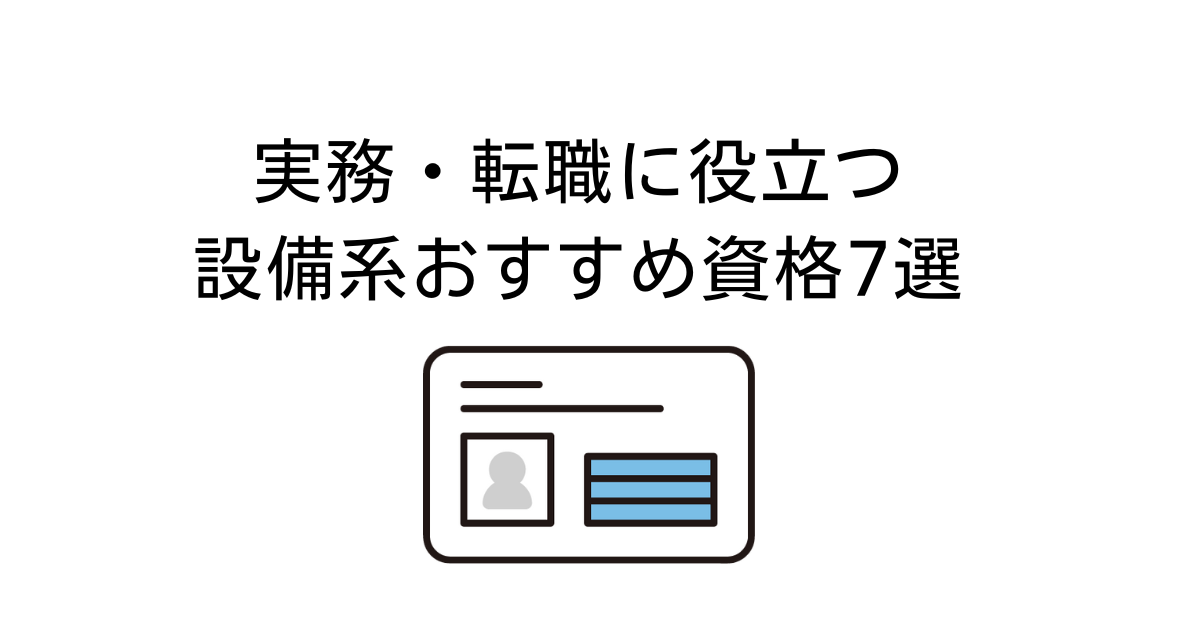


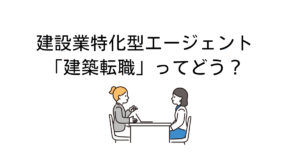
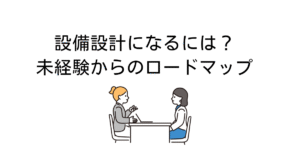



コメント